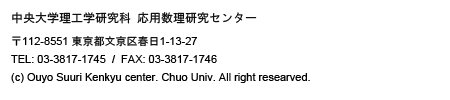応用数理研究センターの概要
現代社会においては、技術革新の加速度的な進展と情報化社会への急激な移行に伴い、あらゆる科学技術分野において工学系の既存技術のみならず、その基盤となる数学そのもののパラダイムを変えていかなければこの様な社会的趨勢に対応できない状況に至っています。
こうした状況に対処するためには、理学と工学、特に数学と工学の今以上の連携、共同研究が必要です。実際に、外国、特に米国においては、数学者の積極的な工学への関与が行われており、理学と工学の分野の共同研究が行われています。しかしながら、わが国、日本においては、残念ながら数学と工学の関係が非常に疎遠であり、共同研究は殆どなされていません。実際に、文部科学省 科学技術政策研究所報告書「忘れられた科学―数学」(2006年5月)において、
- より多くの数学研究者が応用分野や実学に興味を持って欲しい
- 応用分野や実学に取り組む数学研究者の育成が必要
- 数学の研究者と他分野の研究者が交流する場が必要
等の意見が寄せられております。
中央大学理工学研究所 応用数理研究センターでは、
- 理工学部における、理学と工学の交流の場を提供する。
- 現実社会における諸問題あるいは工学における諸問題(環境問題、人口予測問題、新しい統計量の提案、情報セキュリティ問題、流体の問題等)の研究を通じて、数学を中心とする理学と工学の融合・交流を図り、この両面より研究を推進する。
- 理工学部の特性を生かし、当センターの活動を通して、数学的感性に基づく応用数学教育の展開を目指す。
- 日本の、理学と工学の連携に関するさきがけを目指し、社会・産業への貢献を目指す。
との目的のもと、学際融合型の研究を行っています。
組織

応用数理研究センターは以下の四つの組織から成っています。
- 理論数理グループ:流体、力学系等の問題等、新しい数学モデルが模索されている萌芽的分野を検討・研究するグループです。
- 情報数理グループ:情報の確実性と安全性を担保する、符号理論、暗号理論を数学理論の立場から扱うグループです。
- バイオ数理グループ:環境動態解析(環境汚染物質輸送拡散問題、水資源水質確保最適化問題等)、医科学、人口予測等における問題の数学的捉え方、数理モデルの構築を行うグループです。
- データ数理グループ:多変量・高次元データ、あるいは大規模データなど様々なデータに関する新たな統計分析法の開発等の研究を行うグループです。
構成メンバー
2008年4月1日現在、応用数理研究センターの構成メンバーは以下の通りです。
| センター長 | 關口 力 | 数学科・教授 |
|---|---|---|
| 幹事 | 大春 慎之助 杉山 高一 松山 善男 百瀬 文之 高倉 樹 |
数学科・教授 数学科・教授 数学科・教授 数学科・教授 数学科・准教授 |
| 理論数理グループ |
三松 佳彦(グループ長) 稲見 武夫 香取 眞理 高倉 樹 中野 徹 松山 善男 三好 重明 |
数学科・教授 物理学科・教授 物理学科・教授 数学科・助教授 物理学科・教授 数学科・教授 数学科・教授 |
| 情報数理グループ |
關口 力(グループ長) 今井 桂子 今井 秀樹 白井 宏 諏訪 紀幸 田口 東 趙 晋輝 百瀬 文之 山本 慎 |
数学科・教授 情報工学科・教授 電気電子情報通信工学科・教授 電気電子情報通信工学科・教授 数学科・教授 情報工学科・教授 情報工学科・教授 数学科・教授 数学科・教授 |
| バイオ数理グループ | 大春 慎之助(グループ長) 樫山 和男 河原 睦人 小林 良和 宗行 英朗 望月 清 |
数学科・教授 土木工学科・教授 土木工学科・教授 数学科・教授 物理学科・教授 数学科・教授 |
| データ数理グループ | 杉山 高一(グループ長) 遠藤 靖 鎌倉 稔成 田口 善弘 宮村 鐵夫 山田 正 渡邊 則生 酒折 文武 村上 秀俊 |
数学科・教授 経営システム工学科・教授 経営システム工学科・教授 物理学科・教授 経営システム工学科・教授 土木工学科・教授 経営システム工学科・教授 数学科・専任講師 経営システム工学科・助教 |